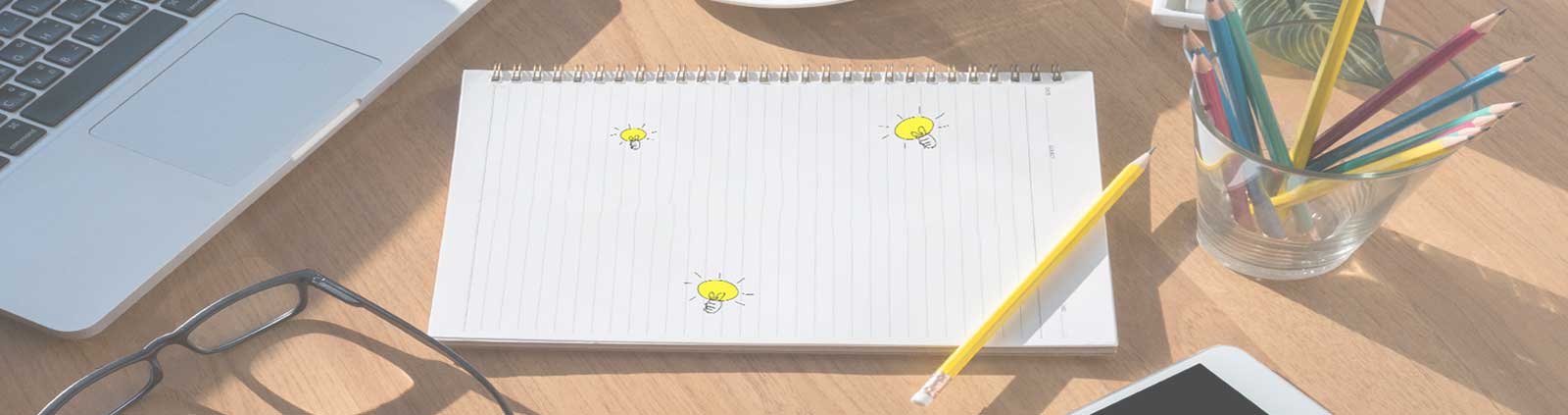
相続・遺言でトラブルにならないための注意点5選

はじめに:相続でなぜトラブルが起きるの?
「うちの家族は仲がいいから、相続でもめることなんてない」と思っていませんか?
でも実は、相続をめぐるトラブルはどの家庭にも起こりうる、意外と身近な問題です。
家庭裁判所の調停件数は令和3年で年間13,447件。20年前より約1.5倍に増えています。
しかも、その多くは遺産総額が5,000万円以下の「普通のご家庭」で起きているのです。
トラブルの原因はさまざまですが、代表的なのは以下のようなものです。
- 不動産をどう分けるかで対立
- 遺言書の内容に納得できない
- 財産の全容がわからず不信感が生まれる
こうしたトラブルは、事前の準備とちょっとした工夫で未然に防ぐことができます。
この記事では、相続でもめないために知っておきたい5つの注意点を紹介します。
注意点① 不動産の共有は避ける
相続でもっともトラブルになりやすいのが不動産。
たとえば実家を兄弟で共有した場合、「売りたい人」と「住み続けたい人」で意見が割れ、なかなか結論が出ません。
さらに、不動産は共有者の1人でも反対すると売却できず、
時間が経つとその共有者の子どもへ相続されて、権利関係が複雑化します。
どうすればいい?
- 共有にせず、単独所有にするのが理想
- 代償分割(現金などで他の相続人に補う)や、換価分割(不動産を売って分ける)も有効
- 共有になってしまった場合も、専門家に相談して「持分買取」などを検討する
司法書士は不動産登記のプロですので、こうした相談も得意です。
注意点② 遺言書の不備や曖昧な内容
「遺言があれば安心」と思われがちですが、書き方を間違えると無効になることも。
よくある失敗例
- 自筆証書遺言で日付・署名・押印が抜けている
- 「埼玉の土地を長男に」など内容が曖昧
- 「預金は子どもたちに」だけでは、口座や割合が不明
さらに、遺言が複数あると混乱したり、「認知症で書いたのでは?」と有効性を争われることもあります。
対策ポイント
- 法律に沿った形式で書くこと(特に自筆証書は要注意)
- 内容はできるだけ具体的に。たとえば「○○銀行○○支店の口座(口座番号)を長女に」など
- 不安なら公正証書遺言を作成するのもおすすめ
- 専門家にチェックしてもらうと安心です
注意点③ 相続人同士のコミュニケーション不足
相続で一番やっかいなのは、感情のもつれ。
多くのトラブルは、「ちゃんと話していなかった」ことから始まります。
典型的なトラブル
- 特定の相続人だけが生前贈与を受けていた
- 一部の兄弟でだけで話が進んでいた
- 「勝手に手続きされた」と感じる
不信感は簡単に拡がります。
注意点④ 遺留分に配慮する
たとえば「長男に全財産を遺す」と遺言に書いたとしても、それが他の相続人の遺留分を侵害していた場合、「遺留分侵害額請求」という形で法的に取り戻される可能性があります。
遺留分って何?
- 配偶者・子・親には、法律で決められた最低限の相続分(遺留分)がある
- たとえば配偶者と子2人なら、遺留分はそれぞれ1/4、1/8、1/8
- 兄弟姉妹には遺留分なし
どうすれば?
- 法定相続人の取り分がゼロにならないように配慮する
- 特別な事情があるなら、事前に説明して理解を得る
- 遺留分の計算が難しい場合や不安な場合は、司法書士や弁護士に相談を
注意点⑤ 自己判断で進めない
相続手続きは、登記・税金・法律が絡む専門的な分野です。
「とりあえず自分たちでやってみよう」と始めた結果、余計に時間とお金がかかるケースも少なくありません。
よくある失敗
- 書類の不備で手続きがやり直し
- 期限を過ぎてペナルティ発生
- 一部の人だけで進めてしまい、他の相続人が激怒
- 遺留分や相続放棄の判断ミス
専門家に任せると安心
- 司法書士:登記や財産整理、相続手続きの全般
- 税理士:相続税の申告・対策
- 弁護士:トラブル対応・調停など
司法書士なら、相続登記から遺言・財産目録・手続きの代行まで幅広く対応可能です。
まとめ:今できることから始めよう
相続は人生の大事な節目。
「準備しておけばよかった」と後悔しないよう、今できることから始めてみませんか?
今日から意識したい5つのポイント
- 不動産は共有にせず単独名義で
- 遺言書は形式・内容を正しく
- 家族で事前にしっかり話し合う
- 遺留分の配慮は忘れずに
- 困ったら専門家に相談を!
相続は「家族への思いやり」をカタチにする行動です。
争いを避け、安心して手続きが進められるよう、私たち専門家がしっかりサポートします。

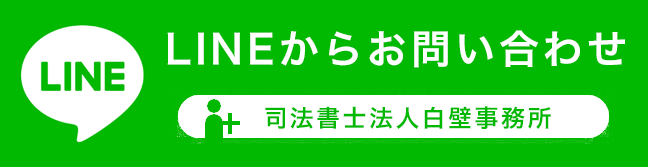
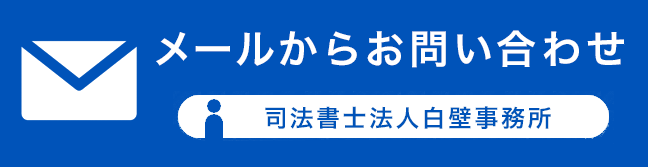
 一覧へ戻る
一覧へ戻る